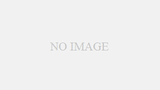匿名での誹謗中傷がネット上に書き込まれたとき、「誰が書いたのか特定できるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。実際、投稿者の身元を突き止めるには「IPアドレスの開示請求」という法的手続きが必要になります。本記事では、誹謗中傷の投稿者を特定するための仕組みと、IPアドレス開示までの流れ、企業が知っておくべき対応のポイントをわかりやすく解説します。
誹謗中傷の投稿者は特定できる?基本的な仕組みとは
インターネット上に書き込まれた誹謗中傷の多くは、匿名や偽名による投稿であるため、一見すると誰が発信者なのか特定するのは不可能に思えるかもしれません。しかし、実際には「プロバイダ責任制限法」に基づく法的手続きを通じて、投稿者の特定を行うことは可能です。
その仕組みの要となるのが「IPアドレス」です。これは、インターネット上の住所のようなもので、誰かがSNSや掲示板に投稿した際、その投稿は必ず何らかのIPアドレスと紐づけられています。サイト運営者(またはサービス提供者)は、このIPアドレスや接続時間などの情報を一定期間保有しており、適切な手続きを踏めば裁判所を通してこれらの情報を開示させることができます。
ただし、書き込みが削除されても、サイト側にはログとして残っている場合があり、証拠さえ保存されていれば対応は可能です。反対に、ログの保存期間(通常3〜6ヶ月程度)を過ぎてしまうと、IP情報が消去されてしまい、特定が困難になるため、対応の「スピード」も非常に重要です。
つまり、匿名であっても完全な“隠れ蓑”ではありません。法的に正当な理由があり、必要な手順を踏めば、誹謗中傷の書き込み主を特定することは十分に可能なのです。
IPアドレスの開示請求に必要な条件と証拠の集め方
IP開示請求は誰でもできるものではなく、あくまでも「権利侵害が明確に認められる場合」に限って行うことができます。具体的には、名誉毀損、プライバシー侵害、信用毀損、業務妨害などが対象となり、「発信者の特定が必要かつ相当である」と裁判所が判断した場合に限り、開示が認められます。
このため、まず必要なのは「誹謗中傷が存在する証拠」をしっかりと保全しておくことです。投稿が行われたページのURL、投稿日時、内容をスクリーンショットで保存し、発言によってどのような権利が侵害されたのかを明確に記録しておくことが求められます。
さらに、証拠だけでなく、「その投稿によってどのような被害が発生したのか」もできる限り整理しておくことが大切です。たとえば、「この投稿をきっかけに問い合わせが激減した」「求人応募が止まった」「顧客から苦情が入った」など、具体的な影響があれば、裁判所が開示を認める根拠となります。
なお、IP開示請求は法律に基づいた“仮処分”として進める必要があるため、弁護士を通じての手続きが一般的です。書類作成や証拠の整理、裁判所とのやり取りなどは専門性が求められるため、個人や企業が独自に進めるのは現実的ではありません。
IP開示請求は“正確で信頼性のある証拠”と“法的な理由”がなければ成立しません。投稿が残っているうちに、迅速かつ正確に情報を収集しておくことが、書き込み主特定への第一歩となります。
開示請求の具体的な流れと期間・費用の目安
誹謗中傷の投稿者を特定するためのIP開示請求には、いくつかのステップが必要です。大まかな流れは次のようになります。
- 弁護士への相談・証拠整理
- 投稿先サイトの運営会社(第1プロバイダ)への仮処分申立て
- IPアドレスや投稿者の接続記録(ログ)の開示
- 通信会社(第2プロバイダ)への情報開示請求
- 住所・氏名などの投稿者情報の取得
- 損害賠償請求や警察への告訴(必要に応じて)
この手続きには、通常3〜6ヶ月程度の期間がかかります。また、場合によってはさらに時間を要することもあるため、初動の早さが非常に重要です。
費用については、依頼する弁護士の報酬や裁判所への申立て費用などを含め、50万円〜100万円程度が一般的な相場です。ただし、複数の投稿や大規模な拡散が絡む場合は、それ以上の費用が発生することもあります。
重要なのは、裁判所が「投稿者特定が正当である」と判断しなければ開示されないという点です。感情的に「許せない」と思っても、法的に認められる証拠と合理性が必要不可欠です。
また、サイトによっては日本に拠点がなく、運営者への連絡や開示が非常に難航するケースもあります。その場合は、海外の法律やプロバイダとのやり取りが必要になり、さらに複雑化します。
開示請求は「確実に相手を特定できる手段」である一方で、手間も時間もかかることを理解したうえで、リスクと効果を見極める必要があります。
投稿者特定後に企業が取るべき対応と注意点
IP開示によって投稿者の身元が判明した後、企業としては次に「どのような対応を取るか」を慎重に判断する必要があります。主な選択肢は以下の3つです。
- 損害賠償請求(民事訴訟)
- 刑事告訴(名誉毀損・業務妨害等)
- 和解や謝罪要求
たとえば、投稿によって実際に売上減や風評拡散などの実害が生じていれば、損害賠償請求に踏み切る企業も少なくありません。また、投稿内容が悪質であれば、名誉毀損罪や信用毀損罪などで警察に告訴し、刑事事件として追及することも可能です。
一方で、投稿者が未成年や元顧客・元社員であるケースもあり、その場合は法的措置に踏み切ることでさらなる炎上リスクや人間関係の悪化を招く可能性もあります。こうしたケースでは、弁護士を通じて謝罪と投稿削除、再発防止誓約を取り付ける「和解」の道を選ぶことも有効です。
企業として重要なのは、「正当な理由があって法的措置を取っている」ことを社内外にきちんと示すことです。対外的に説明が曖昧だと、むしろ企業イメージを損なうリスクもあります。
さらに、特定後の対応は一時的な問題解決にとどめず、「再発防止」や「ブランド保全」に活かしていく視点が大切です。投稿者の特定はゴールではなく、“信頼を取り戻すスタート地点”と捉えるべきでしょう。
まとめ
ネット上の誹謗中傷は匿名で行われることが多いものの、法的手続きを正しく踏めば投稿者を特定することは可能です。IPアドレス開示請求はそのための重要な手段であり、証拠の確保とスピーディーな対応が鍵となります。ただし、開示までには時間と費用がかかるため、弁護士と連携したうえで戦略的に進めることが求められます。特定後の対応も冷静かつ適切に行い、企業としての信頼を守る一貫した姿勢が何より大切です。